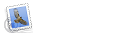スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編
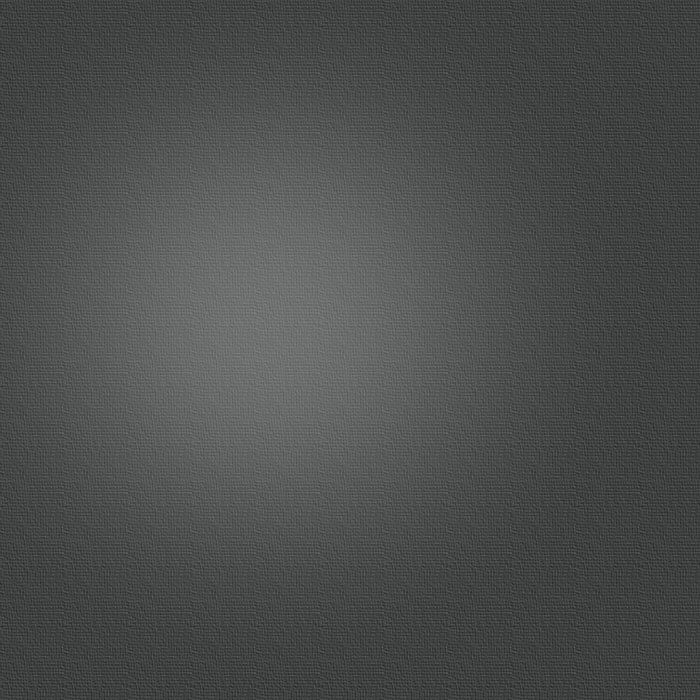
トニー賞演劇部門で6つの賞を獲得した「レッド」はマーク・ロスコの苦悩を描いた秀作である
2010年6月12日土曜日

ブロードウェイで上演されている「レッド」のことは、上演開始から気になっていたのだけど、なかなか時間がなくて見に行くことが出来ないでいるうちに、なんと、トニー賞演劇部門で、最優秀作品賞を含めて6部門を受賞してしまった。しかも、公演は6月27日まで。あわてて劇場に駆けつける。
「レッド」は、僕が心から愛するアメリカのアーチスト、マーク・ロスコを主人公にした舞台である。マーク・ロスコについては、以前のブログで何度か紹介したのでこちらを観て欲しいのだけど(「マーク・ロスコ:色との対話、超越性への誘い」、「Rothko Chapel:瞑想、祈り、対話の空間」)、1950年代を中心に米国で活躍した抽象表現主義の画家で、その独特の抽象画で多くの人の心を魅了した画家である。
「レッド」は、1958年から1961年までの3年間のロスコの姿を、彼の助手の男性の目から描いた作品である。舞台は、ロスコの絵が無造作に置かれた彼のスタジオ。登場人物は、ロスコと助手の2人だけ。舞台は、二人の対話のみで進行する。とてもシンプル。

1958年は、ロスコが、フォー・シーズンズ・レストランの壁画を委嘱された年である。以前のブログでも紹介したように、ロスコは、この壁画が、スノッブなニューヨーカーが食事をする場所でただ消費されることに耐えられず、作品を納入した後、結局これを買い戻すことになる。それまでの3年間がとりあえず、この舞台を流れる時間だと要約できるだろう。そこで、ロスコは、批評家やギャラリーのオーナーや、ロスコの絵を求める富豪達の俗物さと無理解に悪態をつき続ける不機嫌で高圧的な天才芸術家として描かれる。
助手が初めてスタジオを訪れた日、ロスコはいきなり助手に自分の絵を見て何を感じるかを尋ねる。助手が、何も言葉に出来ずにまごついていると、ロスコは、「お前は本を読まないのか。お前には教養がないのか。文学、過去の名画、何でも良いからとにかく学び続けろ。教養がなければ、創造は不可能だ。」とどなりつける。そして、「俺はお前の父親でも教師でも友人でもない。雇い主だ。それを忘れるな。」と言い放つ。その後も、ロスコは、徹底的に、不機嫌で、世界のすべてに悪態をつき続ける天才的な人間として描かれる。そして、助手に当たり散らす。しかし、やがて、徐々に、二人の間に信頼感が芽生えていく。。。。
印象的な台詞がある。ロスコが、「黒は赤を飲み込もうとする」と呟く。これに対し、助手が、「あなたは、黒を怖れているのではないか。赤は生命の色だ。それに対し、黒は死を意味する。あなたは、黒を怖れることで、死を怖れているのではないか。」と尋ねる。これに対し、ロスコは、しばらくの間をおいて、このように応える。「それは、心理学的な解釈に過ぎない。お前にはアートをアートとして理解することが出来ていない。私にとって、黒とは、大英博物館にかかっているレンブラントのあの漆黒の黒だ。あの光の背後に広がる無限の黒だ。」と応える。そう、たしかに、ロスコは、色によって思考した画家であった。
舞台は、最後、ロスコが、フォー・シーズンズの絵を買い戻し、助手を首にするところで終わる。唐突に首にされた助手は、困惑してロスコに食ってかかる。これに対して、ロスコは、次のように応える。「首にするのに理由などない。ただ自分にはアシスタントが必要なくなっただけの話だ。お前はこのスタジオでこれ以上私と一緒にいる必要はない。俺がお前の年には、失うものなど何もなかった。ただアートと、ビジョンだけがあった。お前は、これから外の世界に出ていろんなことを経験しろ。そして、何でも良い。一つ、新たなものを世界に付け加えるんだ。」

「レッド」は、ロスコを主人公にしながら、師と弟子の物語として読むことが出来るかもしれない。師は、何も教えないけれど、ある時が熟したとき、弟子に別れを告げる。何かが明示的に教えられたわけではないけれど、ある時間を共有することを通じて、言葉では伝えることが出来ない、あるかけがえのないものが師から弟子へと伝えられ、弟子はイニシエーションを終えて世界に向かって旅立ってゆく。。。。
あるいは、単純に、「レッド」は芸術家の苦悩の物語なのかもしれない。世間の通俗さに耐えきれず、また、新たに台頭しつつあるポップ絵画に苛立ちながら、独自の芸術を追究し続ける孤高の天才の物語。ジャクソン・ポロックの死に自殺の影を感じ、自分もかつてそのように孤独と絶望のうちに死を選ぶのではないかという予感に怯えながら(実際、彼は最終的に自殺する)、作品制作を続けるアーチストの実存的不安の物語。
ロスコを心から愛する私にとっては、「レッド」におけるロスコの人物造型や物語があまりにも類型的すぎて(ニューヨークの評論家は、この手の芸術家の苦悩の物語が本当に好きなんだけど、その物語自体が、「レッド」で批判の対象にされている「通俗性」でしかないことにどうやら批評家達は気づいていないようです。)、ちょっと退屈したけれど、まあ、良い作品だと思います。特に、トニー賞でも受賞した舞台照明が素晴らしい。赤と黒だけのロスコの作品が、照明の微妙な変化によって、その色調を変えていく、その変化がただ繊細で美しく、息をのみます。一瞬の照明の変化で、ロスコの単調な絵の「赤」が、強烈な血を思わせる「赤」となり、あるいは、生命力そのものを感じさせる鮮やかな「赤」に変容します。また、時には、その「赤」の背景でしかない「黒」が鮮やかに自己主張を始めたかと思うと、禍々しいまでに強力ですべてを飲み込もうとする「黒」に変容します。舞台上で単調に繰り返されるロスコと助手の対話には、少々うんざりさせられますが、この繊細な照明の造型には本当に心を揺さぶられます。

ロスコは、「レッド」の時代を経て、その後、より暗い青や黒へとその色彩を変化させていきます。論者によっては、赤から黒への変化をロスコの精神的鬱屈に求める人もいます。しかし、ロスコ自身は、「黒」に積極的な意味を見いだしていたようです。ちょうど良いタイミングで、ナショナルギャラリーが「マーク・ロスコ」展をやっているので最後にこれを紹介しておきましょう。この展覧会は、ナショナル・ギャラリーのタワー最上階のホールにロスコの晩年の黒や青を中心とした作品を展示し、同時に、ロスコ・チャペルが出来たときにモートン・フェルドマンが作曲した「ロスコ・チャペル」という作品を聞かせるという企画です。テーマはもちろん、ロスコの黒です。ロスコ自身の言葉を借りれば、「黒は闇ではなく、光である。自分は、これらの作品を通じて、黒の輝きを描きたかった。」とのことです。
実際、ロスコの晩年の暗い色調の作品の前に佇むとき、僕は、深い宗教性と精神性をそこに感じます。それは、鬱屈や苦悩などとはほど遠い、静謐で緊張感と安らぎが同居した深みのある世界です。たぶん、「レッド」の舞台が物足りないとすれば、それは、晩年のロスコが到達したこの「黒」の境地を舞台上に描くことが出来なかったためなのかもしれません。


レッドを上演しているゴールデンシアター外観