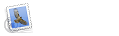スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編
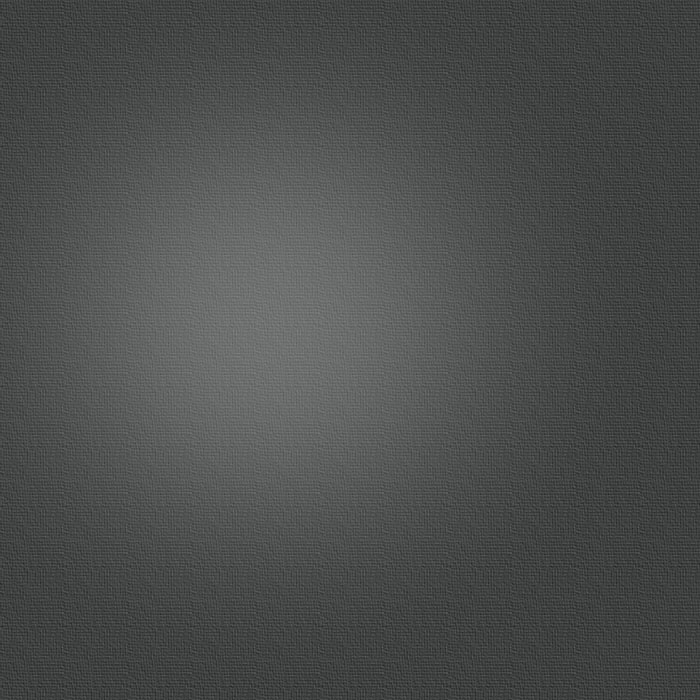
バルド(中有):チベットの死者の書が描く生と死の中間領域
2010年4月10日土曜日

チベット仏教の基本的な経典の一つであり、また、欧米諸国でも広く読まれているものの一つに「チベットの死者の書」があります。これは、チベット仏教徒であれば誰でも知っている、人が死んでから次に転生輪廻して生まれ変わってくるまでの間の49日間の旅の様子を描いた作品です。日本でも、「四十九日」と言う形でこの信仰が残っているから、大体おわかりいただけると思います。
チベットでは、人が死んだら、その「魂(仏教では、人間の魂の実在を否定するので、本当はこの言葉は正しくないんだけど、まあ、ここでは、ごく日常的な意味で、人間の意識が死んだ後にその身体を離れて浮遊する状態を魂と呼んでおきます。)」は、頭頂から抜け出て、「バルド=中有」の状態に入ると信じられています。このバルドをいかに正しく過ごすかが、死者の解脱や次の転生に大きな影響を与えると考えられています。このため、チベットでは、人が死んだら、「バルドの期間=四十九日の期間」、残された家族はチベット僧を招いて、死者の側で「チベットの死者の書」を読経してもらい、死者の魂が、迷うことなく解脱できるように、あるいは少なくとも、餓鬼や畜生界に落ちることなく良き転生に恵まれるように努めます。これがバルド信仰です。

バルドの期間は幾つかの段階に分かれます。詳しくは、「チベットの死者の書」の日本語訳を見ていただくことにしたいと思いますが、最初、死者の魂は、自分が死んだことを認識せず、死体の周りを浮遊しています。自分の死体が安置され、周りで親族や友人が嘆き悲しんでいるのを見て驚き、時には自身の肉体に戻ろうとします。しかし、ここで、自身の身体に執着したり、あるいは親族や友人に未練を残しては、死者の魂はちゃんとバルドへの旅に赴くことが出来ません。時には、そのまま、室内に居着いてしまい、残された家族に禍をもたらすこともあります(日本で言うところの不成仏霊ですね。)。だから、チベットの者の書では、死者が死んだら、あまり親族や友人は大騒ぎして嘆き悲しんだり、あるいは死者の名を呼んだりしないように戒めます。逆に、僧が、読経を通じて、死者に対し、「あなたはすでに死んでいるのだから、現世に執着することなく、これからのバルドを有意義に過ごして、解脱に向けた貴重な機会であるバルドの期間を、道を誤ることなく過ごすように教えます。
では、バルドの期間、死者の魂はどのような経験をするのでしょうか。基本的に、死者の魂は、バルドのそれぞれのステージにおいて、とどろき渡る雷鳴のような大音響と目も眩むような強烈な光の塊に出会います。それぞれのステージにおいて、この光の塊の色は異なります。なぜなら、それぞれのステージは、チベット仏教の教えに基づく、様々な仏や守護神の領域だからです。いずれにせよ、死者の魂は、このような光の塊に出会って、恐れおののき、そこから逃れようとします。しかし、ここで、その光の塊から逃れては、解脱は得られません。むしろ、生きていたときの教えを守り、信仰を堅持して、その光の塊が仏性の顕現であり、その光に参入し、それと一体化して、初めて解脱を得ることが出来るのです。「チベットの死者の書」は、死者の魂が、きちんとバルドの旅において解脱を得ることが出来るよう、死者の魂に語りかけ、旅を導いてやる指南の書だと言えるでしょう。

しかし、普通の人は、やはり恐怖を克服することが出来ず、光と一体化して解脱を得ることが出来ません。そのような魂は、結局、バルドの旅の終わりに再び現世に戻ってきます。「チベットの死者の書」は、そこでもまた死者を教え導いて、死者が「地獄」「畜生」「餓鬼」に生まれ変わらないようにしてやります。面白いのは、チベット仏教では、人間界よりも上位にある「天上界」や「阿修羅界」ではなく、「人間界」に生まれ変わることを推奨する点です。現代人の視点からすれば、苦しみの多い人間界ではなく、天上界や阿修羅界に生まれ変わる方が良いと思うのですが、チベット仏教では、ただ人間界だけが、解脱に赴くことの出来る唯一の世界であり、苦しみこそが解脱への動機となると考えるからです。面白いですね。
チベットの死者の書は、最後、人間界に生まれ変わる様子を生々しく描きます。死者の魂は、バルドの旅の最後、これから自分の両親となるはずの男女がセックスしているのを眼にします。そこで、男性の方により惹かれれば魂は女の子として、女性の方により惹かれれば男の子として生まれてくるそうです。迷信だと言えばその通りですが、チベット仏教では、セックスで受精した瞬間に生成するのはあくまでも生物的な受精卵でしかなく、そこに意識が生じるのはバルドの旅を終えた死者の魂がこの受精卵にいわば「受胎」するからである、と考えているから、論的必然としてこのようになるわけです。身体と精神の二元論をこのような形で説明しようとするのは、チベット仏教の合理性を表していると思います。

以上が、チベット仏教における「バルド」の教えです。余談ですが、この「バルド」の旅が、人間にとって、解脱する可能性がある貴重な機会であるという信仰はチベット仏教、特にゲルク派には根強く、このバルドをうまく旅をするための「死の技法」が高度に発達しました。「死の技法」といっても、別に自殺をするわけではなく、瞑想を通じて、「死」を仮想体験し、バルドに備えようという修行です。これが、ゲルク派の最高の奥義といわれる「グヒヤサマージュ(秘密集会)」の実践の根本をなしており、この修行において、人は、生から死への移行を仮想体験します。興味がある方は、「ゲルク派版 チベットの者の書」などを読まれると良いでしょう。
さらに余談ですが、「バルド」への良き旅を行うためには、死んだ後、魂が、身体のどこの部位から外に出るかが重要なポイントだとチベット仏教は考えました。人間の身体には多数の穴があります。口、鼻、耳、肛門・・・。しかし、このようなところではなく、身体の中心を走る脈管の頭頂部から外に出るのがもっとも正しい魂の脱出方法であるというのがチベット仏教の信仰です。死に際してきちんと魂を頭頂部から外に出すことが出来るよう、チベット仏教徒は生きている間にこのやり方を練習します。これが、「ポアの技法」と呼ばれるものです。オウム真理教のせいで日本では激しく誤解されてしまいましたが、「ポアの技法」は正式には、このような良き死への準備作業なのです。実際に、バルドへの旅路において、「ポアの技法」が有効であるかはともかく、この技法は、クンダリーニヨガの脈管の操作法にも通じますし、何よりも人が近づきつつある自分の死と向かい合い、これを精神的に受け入れてこの世に未練を残すことなく正しく死んでいくために必要な手続きとして意味があると思います。
以前にもこのブログで議論しましたが、近代社会は、死を社会的に隠蔽し、抑圧することによって、結果的に、人が、死と向かい合い、これを受け入れるようにするための社会的な仕組みを喪失してしまいました。これを回復するために、今、様々な宗教団体や医療関係者が、「終末医療=ターミナルケア」に取り組んでいます。チベット仏教でも、これに取り組んでいる団体はあります。その際には、このポアの技法なども参考になるのではないかと思います。
ここまで、延々と「チベットの死者の書」の紹介をしてきましたが、実はこれは前置きで、本当は、現在、ルビン美術館で開催されている「バルド」展の紹介をするつもりだったのです。でも、もう、これだけ紹介すれば十分ですよね。もしも、ニューヨーク在住の方がおられれば、ぜひ観に行かれることをお勧めします。チベット仏教のおどろおどろしい憤怒尊や骸骨などが、実は、チベット仏教の独特の死生観に裏打ちされ、高度に発展したシンボルの体系であることが理解できます。


ヘルーカ憤怒尊。バルドの守護神。