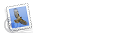スピリチャルでアートな日々、時々読書 NY編
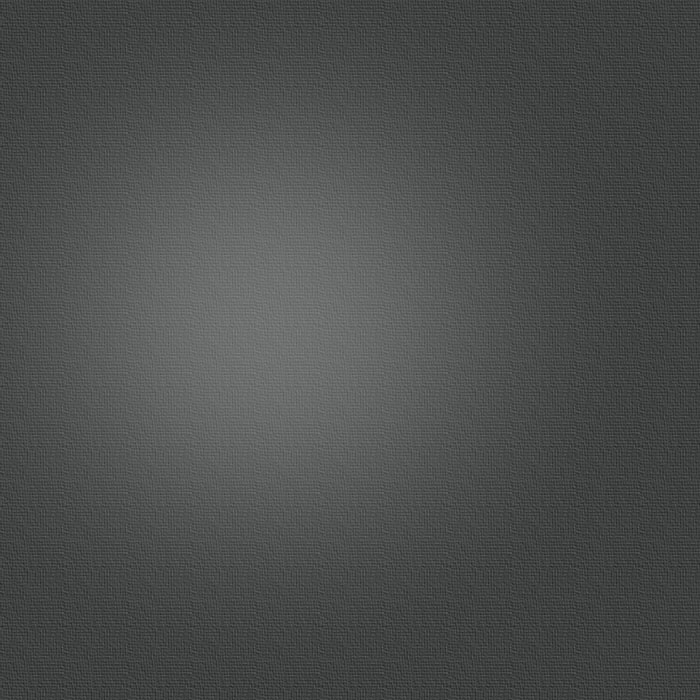
ヘンリー・ダーガー再び。あるいはマンダラ世界の誘惑
2009年5月31日日曜日

久しぶりに、アメリカン・フォーク・アート美術館に行く。ヘンリー・ダーガーの特集展示を観るのが目的。ちなみに、ヘンリー・ダーガーとフォークアート美術館については、以前に一度、ブログで解説したので、関心がある人はそちらを読んでください。
ヘンリー・ダーガーという人の作品は、ほんとにユニークで、何度観ても発見がある。よくまあ、これだけ、と言うくらい、いろいろなキャラクターを登場させ、いろいろな場面が出てくる。少女の裸体が大量に描かれており、そこには死と暴力が満ちているのだから、もちろん、その想像力には暗い欲望が潜んでいるはずなんだけど、その色調はあくまでも明るくポップである。それが、ダーガーという、素人画家の持っていた知識と技術の限界のせいなのか、それとも、彼の欲望自身が特殊なものだったのかが、僕には気になる。あるいは、童貞だったのではないかと言われているダーガーは、セックスに至らない未分化で原初的な欲望を、制作を通じて膨らませていったのかもしれない。
ダーガーのこの欲望は、現代日本に氾濫する「萌え系」のアニメやマンガに通じる世界である。ダーガーの世界には、「ショタコン」あり、「変身ヒロイン」あり、「ロリコン」あり・・・と、本当に、現代日本に性的欲望の対象となる者たちの原型が多様に描かれている。なぜ、60年代から70年代にかけて米国の自室でひっそりと個人的な制作を続けていた人間の欲望が、高度に資本主義を発展させてついにガラパゴス化の隘路に入ってしまった21世紀の日本社会の欲望に通じてしまうのか、という問題設定に、僕の想像力は刺激させられる。つい、社会学的な説明ではなく、スピリチャルにこれを説明したい欲望に駆られる。


ところで、全然期待していなかったんだけど、同じフォーク・アート美術館で開催されている「キルトの万華鏡:ポーラ・ネーデルスターンの世界」がすごく良かったので、紹介しておきます。画家は、1951年生まれ。キルト作品を制作していたんだけど、万華鏡の世界に魅せられて、以来、これを主題にした作品シリーズをずっと発表しているとのこと。中には、雪の結晶をテーマにしたものもある。キルトで作られたとはとても思えない複雑で繊細な紋様はとても印象的。


作品を観てもらえればわかると思うけど、この万華鏡の世界、密教が育んできたマンダラの世界に通じるものがあるような気がする。もちろん、マンダラ自身が、古代社会のシンプルな呪術的紋様に発想を得て、これを組織的に展開してきたものだから、それ自身が、人類の意識の古層に根ざしたものである。だから、万華鏡の世界とマンダラの世界が、そういう人類の意識の古層に触れる何者かを媒介に共鳴し合うのは当然と言えば当然なんだけど、でもどうしてこのような紋様が私たちの心の奥底を揺さぶるのだろうか。チベット仏教では、人が死んで次の生に生まれ変わるまでの49日間、人の精神はバルド(中有)と呼ばれる世界を経験すると言われている。そこで、人は、このような光の爆発的な戯れを目にするそうだ。もしかしたら、万華鏡やマンダラの世界に心が揺さぶられるのは、そういうバルドの記憶が心の奥底で甦るからなのかもしれない。
ついでに、面白いな、と思ったのは、万華鏡の発明が、実は19世紀とつい最近の出来事だったという事実。18世紀から19世紀にかけて、西洋は大規模な光学装置の発明・革新を行う。写真、映画はもちろんのこと、カメラ・オブスクラ、ダケレオ・タイプ、幻灯機、ソーマトロープ、パノラマ、ジオラマ・・・と、視覚を再編する様々な仕掛けが考案される。視覚の変容を巡るこの大がかりな欲望の追求の延長上に、現在のアートのみならず、社会が存在していると言っても過言ではない。こうした大がかりな発明と再編の中に、ひっそりと万華鏡が入っていて、密教が育んできたマンダラ世界をプライベートに楽しむ装置を提供し、それがアートの世界に影響を与えた・・・・という歴史の流れに想像を馳せるのもかなり知的刺激に満ちたものになりそうですね。とても僕の手に負えるような簡単なテーマではないけど、もしも、誰か、こういうものを分析した本を知っていたら教えてください。
とまれ、この「万華鏡」展、なかなか良い企画です。ご関心があれば、ぜひ観に行くことをお勧めします。

「ヘンリー・ダーガー」展の入り口